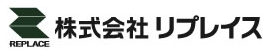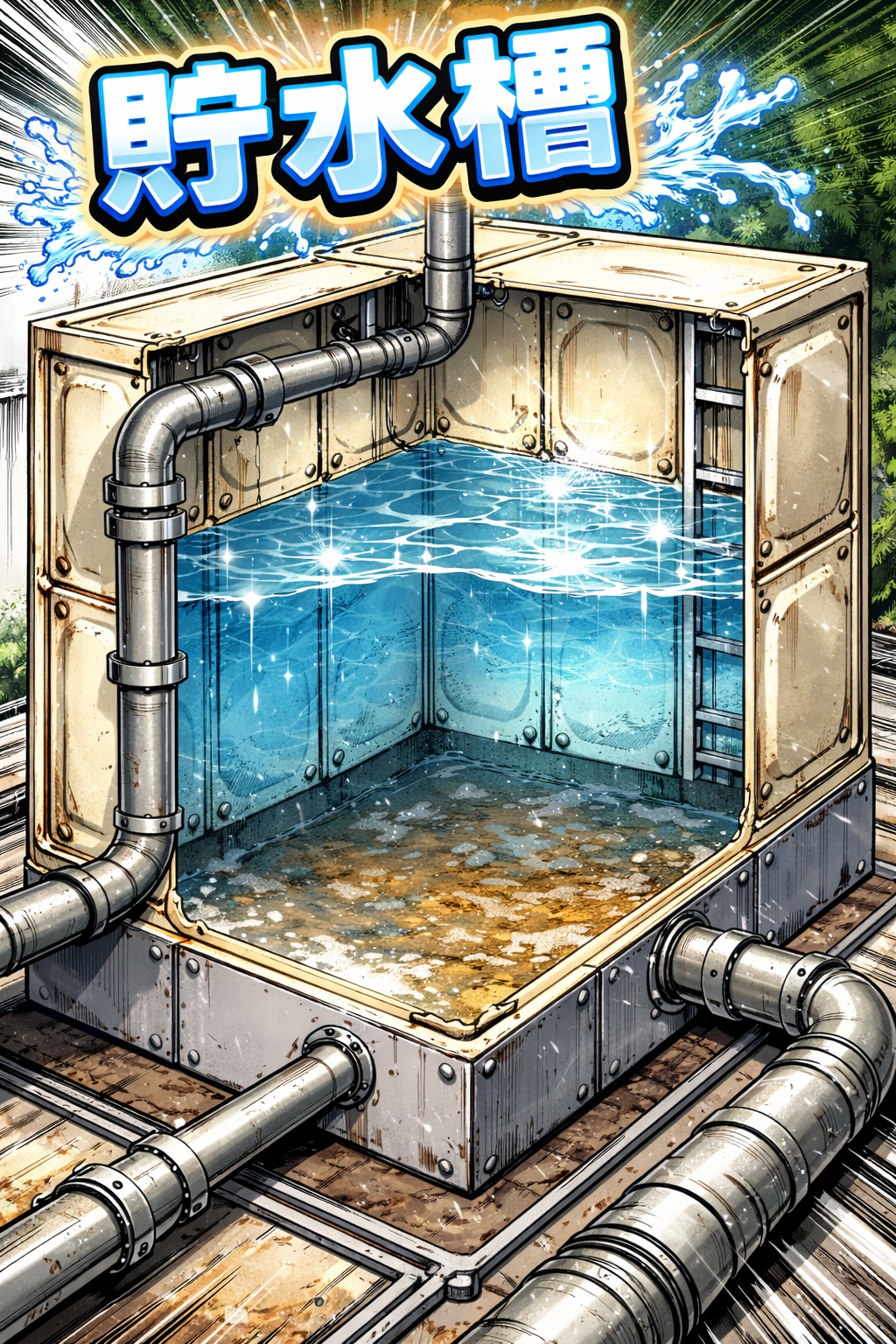マンションの管理形態・第三者管理ってなに?
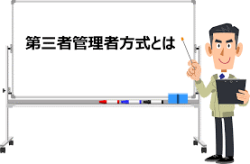
マンション管理といえば、区分所有者が管理組合を組織して運営を担う「理事会方式」が一般的でした。しかし最近では区分所有者の高齢化や住戸の賃貸化が進んだことによって、マンションの役員のなり手不足が深刻化しています。
そのような中で、最近注目を集めているのが「第三者管理者方式」です。
そこで今回は「第三者管理者方式」がどのようなものなのか、お伝えしたいと思います。
1.「第三者管理者方式」とは
「第三者管理者方式」とはその名の通りマンションの管理を第三者である外部専門家に委ねる方法です。従来、マンションの管理は区分所有者で構成する「理事会方式」を採用し、管理組合から選任された理事長と役員によって、建物や敷地の管理を行っておりました。
しかし、区分所有者の高齢化や役員のなり手不足から、理事会そのものが機能不全となるマンションも少なくありません。
そこで、新たな管理方式として導入され始めているのが、「第三者管理者方式」です。理事長や役員に代わり、マンションの日常的な管理から修繕計画の策定、管理費等の管理、区分所有者への報告まですべての管理業務を専門家である第三者が担います。第三者への委託先としては、マンション管理会社、マンション管理士、弁護士、税理士、建築士などが考えられます。
2.「第三者管理者方式」のメリット
Ⅰ.区分所有者の負担軽減
理事会活動の実務的・心理的負担は非常に大きく、参加できない区分所有者も少なくありません。管理・運営がうまく機能していないマンションも多く負担軽減は大きなメリットです。
Ⅱ.管理内容の適正化
定期的なメンテナンスや大規模修繕工事の実施などマンションの管理には専門的な知識が必須です。マンション管理の専門家が進めるのであれば業務の効率化・合理化、管理の適正化が期待できます。

3.「第三者管理者方式」のデメリット
Ⅰ.管理費の増加
管理費の増加がひとつめのデメリットです。第三者管理者方式を導入すれば外部専門家への報酬が必要になり、その委託費は月々の管理費に上乗せされます。
Ⅱ.利益相反行為の可能性
業務委託された専門家は区分所有者側に立って発注しなければならず、受注者側の利益を求めることはできません。専門家が自社で工事を受注する場合や、バックマージンを受け取ることを条件に特定の会社に発注する場合は、利益相反行為が生じる可能性があります。
4.まとめ
第三者管理者方式は理事のなり手がいないマンションを、適正に管理するために有効な手段だといえます。すでに投資用マンションやリゾートマンションで一般化していますが今後は居住用マンションにも普及していくことが予想されます。ただし、外部管理者の選任と管理監督また、発生するコストへの見極めも必要となります。最終的な判断は区分所有者の責任においてなされることとなります。